ストレージアクセス
Contents
ストレージアクセス#
podリソースにて、コンテナを呼び出すことができることはわかりました。 しかし、コンテナは状況によってはデータをコンテナ独自で保持したいと思うときがあります。 Dockerの所ではホスト側のストレージ(ディレクトリ)を共有することや、Docker Engine側で持つストレージを一部渡すことで実現していましたが、K8sの場合でもある程度可能です。
ここではいくつかそれを提示していきたいと思います。
コンテナに付随するストレージ#
コンテナに付随するストレージとしては、 とりあえず2つの方法があるので、ここから学んでおきます。
emptyDirコンテナエンジンから適当に「空のディレクトリ」の割り当てを受けます
hostPathコンテナエンジンの特定のディレクトリを割り当てます
既に存在しているディレクトリだった場合は引き継いで参照できます
emptyDir はコンテナが生成されたときに空のディレクトリを割り当ててもらうため、ポッドを削除した場合は一緒にその存在も消されてしまいます。ポッドがエラーなどで落ちて再起動した場合は落ちる前の状態の割り当てを受けられます。
hostPath は特定のディレクトリを指定できるため、他のPodが使っているディレクトリでも一致すればマウントできてしまいます。同一ノード内でデータの受け渡しをするというときには便利そうですが、 全てのPodが同一ノードで稼働する保証はまったくないという前提を忘れないでください。
ストレージをPodに持ち込む方法#
ではPodのマニフェストに対して、ストレージを設定してみます。 ストレージを設定する方法は2段階で行います。
利用したいストレージを
volumeキーの値として登録します。配列の値で記述し、複数のストレージを定義できます。volumeで登録したストレージ名をPodのspecにてvolumeMountsで登録します。
まずストレージを定義するところを提示します。
spec:
volumes:
- name: empty
emptyDir: {}
- name: hp
hostPath:
path: /data/pv0001
ストレージにはそれぞれ名前(
name)が必要ですストレージが利用する方式と、方式に求められるパラメーターが必要です
emptyDirは何もパラメータを付けなくてもいいのですが、YAMLの記述上値無しが構文エラーになってしまいます。そのため空の値({})を渡すことで回避していますhostPathはコンテナエンジンの動いているホストにおいての適当なディレクトリを指定します
Caution
minikubeによるK8s環境では、停止(minikube stop)させたときにhostPathで指定したディレクトリは自動的に消去されます。
ただし、データを残したいというときもあるため、 /dataディレクトリなど、一部のディレクトリは次回の環境起動時にも再現される仕組みを採っています。
詳しくは永続ボリュームを参照してください。
Pod側のマウント#
Pod側でのマウントは、 volumeMounts を使って行います。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: storagepod
labels:
name: storagepod
spec:
volumes:
- name: empty
emptyDir: {}
- name: hp
hostPath:
path: /data/pv0001
containers:
- name: stragepod
image: alpine
resources:
limits:
memory: "128Mi"
cpu: "500m"
command:
- "/bin/sleep"
- "infinity"
volumeMounts:
- name: empty
mountPath: /data/empty
- name: hp
mountPath: /data/hp
Pod側は、ストレージがどういうシステムで構成されているかは意識せず、あくまでvolumesで登録したキーに対するマウントポイントという形で行います。
Note
せっかくなので、マニフェストをコピーし、ポッド名などだけを書き換えたポッドを作ってみましょう。 このとき、2つのポッド(上で作ったものと名前を書き換えただけのポッド)のストレージを書き換えたとき、他方でその内容が参照できるでしょうか?
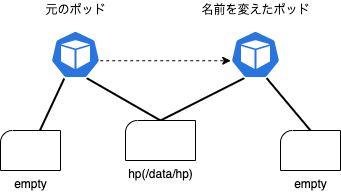
Fig. 12 2つのポッドが同じパスを参照するhostPathを定義したときの様子#
Tip
minikubeの中でファイルを作成した場合、それを直接取得するのはかなり難しいです。 本番環境では、ファイルを作成したときのストレージをローカルから参照できるものをソースに設定して、コマンドで取得するようなケースが多いようです (たとえばAWSのS3ストレージがマウントできるので、S3ストレージにに保存されたデータをバックアップマシンからアクセスする等)。
.png)